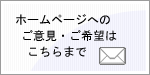会長挨拶
川原 顕磨呂
KAWAHARA Akimaro
2025年度総会におきまして、第39期日本混相流学会の会長を拝命いたしました。身に余る光栄であると同時に、その責任の重さに身の引き締まる思いでおります。
混相流という複雑かつ多様な現象を対象とする本学会は、機械工学、化学工学、原子力工学、土木工学、環境工学、医療・バイオ工学など、幅広い分野にまたがる学際的な知の集積の場として、これまで重要な役割を果たしてまいりました。私自身、混相流の研究に携わってから長い年月が経ちました。原子炉燃料集合体内のサブチャンネル間のクロスフローの研究から始まり、マイクロチャンネル内の二相流、マイクロバブル・ミストの発生器の開発・応用に関する研究を行ってきましが、混相流の奥深さと未解明の魅力に、今なお心を惹かれ続けております。気泡、液滴、粒子、界面、乱流、相変化など、混相流を構成する要素は多岐にわたり、それらが織りなす現象は、自然界から産業応用に至るまで極めて多様です。よく言われますが、混相流はまさに「複雑系」の宝庫です。こうした現象に挑む研究者の姿勢は、まさに「未知への探究心」と「理論と実験の融合」に支えられていると感じています。
本学会の国内でのメインイベントである混相流シンポジウム(2000年~2012年は混相流学会年会講演会として開催)や、国際イベントである混相流国際会議(ICMF)は、活発な議論と交流の場として定着しています。私はこれまで研究企画委員会の幹事および委員長として、皆様のご協力のもと、2008年の会津大学での混相流シンポジウムから今年に至るまでのオーガナイズドセッション(OS)企画、ICMF2023(神戸)でのOS企画などを通じて、学会活動の活性化に尽力してまいりました。研究企画委員会は15の分科会から構成され、各分科会が専門性と創造性を発揮しながら、本学会の知的基盤を支えています。分野横断的な活動を通じて混相流研究の裾野は広がり、若手研究者の参画や国際連携も進展しています。こうした多様性と融合こそが本学会の強みであり、今後の発展の鍵と考えています。「多様性の尊重と融合の促進」を基本理念とし、分野間の垣根を越えた協働をさらに推進するとともに、発展が著しいAIやデータ科学との連携、環境・エネルギー問題への応用、国際的な発信力の強化など、混相流の可能性を社会と結びつける取り組みにも力を注いでまいります。
一方で、現在の学会運営においては、会員数の減少や財政面などの課題にも直面しています。これらの課題に対しては、若手研究者や学生の参画促進、産業界との連携強化、学会活動の魅力向上など、持続可能な運営体制の構築に向けた取り組みが不可欠であると認識しております。
2025年の混相流シンポジウムの開催にあたり、実行委員長である神戸大学の林公祐先生をはじめ、実行委員の皆様には企画・運営に多大なるご尽力を賜りました。円滑な運営と充実したプログラムの実現に向けた皆様の熱意と努力に、心より感謝申し上げます。また、2024年度会長を務められた細川茂雄先生、総務部会長として学会運営を支えてくださった村川英樹先生、そして第38期役員の皆様には、学会の発展と安定に向けて多方面にわたるご尽力を賜りました。そのご功績に深く敬意を表するとともに、厚く御礼申し上げます。
会員の皆様のご支援とご協力を賜りながら、混相流という魅力的な研究領域を通じて、学術と社会の架け橋となるよう、微力ながら尽力してまいります。そのためには会員の皆様・理事・委員のご支援、ご協力が必要です。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
熊本大学大学院先端科学研究部 教授